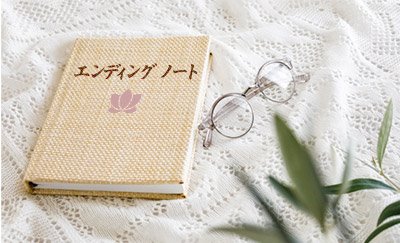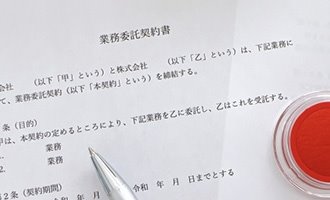高齢化が進む日本において、特に家族など身寄りがない方々は、自分が死亡した後に発生する諸々の手続きはどうなるのか?どのような準備が必要で、誰に相談すればよいのか?といった不安を覚えることがあるのではないでしょうか。
本コラムでは、そのようなケースを想定して、万が一の場合に備える手立ての一つである「死後事務委任契約」の必要性や注意すべき点、契約内容のポイントについて解説します。
また、
死後事務委任契約書の雛形(テンプレート)もダウンロードできますので、合わせてご利用ください。
無料で6,000以上の
テンプレートをDLするなら!
>会員の方はこちらからログイン
死後事務委任契約の必要性とは?
「そもそも自身の死後の事務委任って何?」ということですが、まず、死後に発生する事務的な手続き等にはどのようなものがあるかを下記にまとめてみました。
- 病院や施設の退院・退所の手続き
- 葬儀・火葬の手配
- 親族や関係者等への訃報連絡
- 埋葬・散骨に関する手続き
- 住民税等税金に関する納税手続き
- 遺品整理に関すること
- 公共サービスや各種契約関係の解約等の手続き
- ペットの引渡し
- 相続財産管理人の選任手続きと遺産相続
自身の死後には上記のような事務的な手続きや精算事項が発生します。
一般的には身内・親族がこれらの手続きを執り行いますが、同居の親族や頼れる近親者がいなかったり、いたとしても迷惑をかけたくなかったりする場合などに、あらかじめこれらの「死後事務」を契約にて第三者などに託しておくことが可能です。
これが、一人暮らしで身寄りのない方が増え続ける社会のなか、注目されるようになった「
死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約って法的に有効なの?
死後事務委任契約は、民法に定められている「準委任契約」という契約行為に該当します。
そこでひとつ懸念事項として考えられることが、民法653条にて定められている「委任契約の終了事由」です。
民法653条の条文を確認すると、「委任」は、委任者または受任者の「死亡」によって終了する、と書かれています。
せっかく死後の事務処理等をお願いする目的で契約した「委任契約」が、委任者の死亡によって契約の効果が無くなってしまうとなると、何の意味もない「契約」を締結したことになってしまいます。
実は、この懸念点については判例があります。
いわゆる「死後事務」に関する事項の委任契約について、民法653条により終了して効果がなくなってしまうかどうかについて争われた事案において、「死後事務委任の契約」は委任者の死亡によって「終了」はしないとの内容の判決が出されました。
つまり、「死後事務委任契約」は、委任者の死亡後もその効力が存続する契約となります。
ここでもう一点、補足的な説明を加えます。
「遺言書」で「死後事務委任契約」的な内容を盛り込むことができないのか?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
遺言者の意向により、遺言書にそのような内容を盛り込んでも差し支えはありませんが、遺言書において法的に拘束力を持たせられる内容というのは、民法にて定められている内容に限定されてしまいます。その中に「死後事務委任」に該当するような内容は含まれていません。
そのため、遺言書にて「死後事務委任」的な内容を盛り込んでも、それが実現するかどうかはわからないというわけです。
遺言書に「誰某に対して死後事務に関する内容を託す」といったことが書かれていても、託された者がそれをおこなう義務はないので、実行しなくても契約違反にはならないということにもなります。
「死後事務委任」事項をしっかりと遂行させるためには、「準委任契約」である「死後事務委任契約」を締結しておくことが重要になります。
死後事務委任契約で定めておくべき内容
「死後事務委任契約」ついては、「死後の事務手続き等を託す契約」ですので、生前に託す内容を明確に定め、受任者によって契約した内容がきちんと履行されるようにしなくてはなりません。
一般的に本契約に盛り込まれることが想定される内容を解説します。
委任する事務内容について
「契約の目的」を達成させるために、死後の事務委任の内容について明記する必要があります。発生する事務手続きや精算手続きについて詳細な内容を記載し、委任する事項を漏れなく定めておきます。
たとえば葬儀の方法などについても宗派や、希望があれば詳細な内容を明記し、希望通りの葬儀を執り行ってもらうようにするなど、契約の目的を達成するために最も重要な検討事項になります。
契約受任者への支払いについて
契約の受任者への報酬の支払い期日を明確にしておく必要があります。契約時に受任者に対して一定の金額を預けておくような契約内容も想定されますが、受任者による預り金の横領・着服や契約が履行されずお金が戻ってこないなどといったトラブルに発展するケースもあるようです。
契約を確実に履行してもらうためにも、支払いの時期については、契約の目的を達成した時点となる「本件事務の委任内容が完了した時」とすることが望ましいでしょう。
委任事務の提供の開始時期について
契約の目的である委任事務は、委任者の死亡により開始しますが、受任者が「いつから委任事務を開始するか」について明記しておく必要があります。具体的には、委任者の死亡の事実を知った時として、「死亡診断書等の死亡を証する書面等にて確認した時」などの記載が想定されます。
費用について
委任事務を遂行するにあたって必要となる費用や精算について、委任者の相続財産から支払いをする旨を明記しておく必要があります。
契約の終了と解除について
「契約の終了」について、どのような事由が生じたときに終了するのか、また、解除についての内容も事前に定めておく必要があります。
契約の終了事由については、「委任事務が全て遂行され完了したとき」とするのが一般的です。
契約の解除事由については、契約が相続人によって死後勝手に取り消されないようにするために、「委任者の相続人から本契約を解除することはできない」という内容や、受任者が契約を継続することが困難な事由が生じた場合を想定した「本契約を解除することができる場合」といった内容を定めておいた方がよいでしょう。
署名・捺印について
署名・捺印については、法的な定めがあるわけではありませんが、契約の当事者である本人が確かに契約した証明力を高めるためには、実印を押印し、印鑑証明書を添付する方法をおすすめします。
収入印紙について
「死後事務委任契約」は、印紙税法の「課税文書」には該当しないので収入印紙を貼付する必要はありません。
契約時の注意点~委任ができないこと
「死亡届」については「死後事務委任契約」によって手続きの委任ができません。
一見、死後の事務手続きとして委任が可能なように思われますが、「死亡届」を提出できる権限者は、戸籍法によって定められた者に限定されています。「死後事務委任契約」によって委任できる手続きではないため、注意が必要です。
死後事務委任契約書の雛形(テンプレート)
死後事務委任契約書の作成にあたっては、雛形(テンプレート)の利用が便利です。
ただし、達成したい目的によって残しておくべきもの、契約すべきことも変わってきます。内容については必要に応じて書き換えましょう。
「死後事務委任契約書」テンプレート紹介
自分が亡くなった後の諸手続きを第三者に任せるための契約書雛形です。
葬儀や納骨、家財の整理、携帯電話などの解約、役所への届け出、親族への連絡等、委託したい事務手続きの内容と、手続きにかかる費用の預託、報酬、報告義務等について定めています。
その他、契約解除や変更等についての条文も設けています。
こうした契約を結ぶことにより、遺族の負担を減らし、手続きをスムーズに進めることが期待できます。
内容は適宜編集してご利用ください。
なお、契約書末尾の管理方法等を記載する後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
<よくある質問>
Q. 死後事務委任契約書はどのような場合に使いますか?A. 本人の死後に発生する手続きや整理を、誰にどのように行ってもらうかを事前に決めておく際に利用します。
Q. 遺言書とはどのように違いますか?A. 遺言書が「財産の承継」を定めるのに対し、死後事務委任契約は「死後の実務手続き」を依頼するための契約です。
Q. どのような手続きを委任できますか?A. 葬儀や埋葬の手配、病院や施設の退去、公共料金・携帯電話・SNSの解約、行政への届出(死亡届・年金や保険など)、遺品整理や住居の明け渡し等が対象です。
Q. 契約書はどのように作りますか?A. 委任内容と範囲を明記した書面を作成し、委任者と受任者が署名・押印します。確実性を高めるため、公正証書として作成するのが一般的です。
Q. 契約を途中で変更・解除できますか?A. 本人の生前であれば自由に変更・解除できます。受任者の事情や信頼関係の変化に応じて見直すことも可能です。
その他の生前対策について
前述した「死亡届」については、もし戸籍法に定められた「同居の親族」や「その他の同居人」といった届出ができる権限者がいない場合には、事前にできる対策として「任意後見契約」という手続きがあります。
「任意後見人」は戸籍法に定められた「死亡届」を提出できる権限者でもあり、「任意後見契約」をしておけば、万が一にも自身が認知症等になってしまった場合の代理人として、様々な代理行為について事前の後見契約によりその内容を定めておくこともできます。
死後事務委任契約を検討する必要がある方は、併せて「任意後見契約」も検討する方がよいケースもあります。また、最近では一人暮らしの高齢者の安否を定期的に確認する「見守りサービス」なども普及しつつあります。
まとめ
「死後事務委任契約」を含めた、いわゆる終活のような様々な生前の対策・準備は、自身がまだ健康で意思能力がしっかりしている間に検討し、準備を整えていくことが重要です。本当に困ってからでは対応ができなくなる可能性もあるからです。
自身の死後の事をどのようにしたいかだけではなく、最期をどのように迎えたいかを含めた準備や検討が大切です。
本コラムが、ご自身の死後のことを心配されている方、終活について考えられている方々の安心につなれば幸いです。
執筆者情報
エニィタイム行政書士事務所 代表 中村 充(行政書士)早稲田大学商学部卒業後大手通信会社に入社、法人営業や法務業務に携わる。2009年に行政書士資格を取得し、2017年、会社設立及び契約書作成に特化した事務所を開業。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等各種専門家との連携体制を構築し、企業活動のバックオフィス業務すべてのことをワンストップで対応できることも強み。
プロフィールを見る >行政書士KIC事務所 代表 岸 秀洋(行政書士・銀行融資診断士)司法書士事務所での勤務を経て、2006年に行政書士試験に合格、2014年に行政書士登録開業する。司法書士事務所勤務時代から約100件以上の会社設立サポートを経験してきたなかで、単なる手続き業務にとどまらない伴走者としてのサポートをしていきたいと考えるようになる。事業計画・損益計画の作成から融資のサポートや資金繰り計画など財務支援までおこなうのが強み。
プロフィールを見る >
関連記事